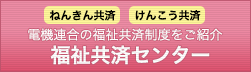研究会抄録

「政治と労働の接点-これからの政治参加の傾向と対策-」
講師:岡崎敏弘様、難波奨二様、オブ参加者様
場所:メロンディアあざみ野(横浜市青葉区)2025年10月17日14時から
発言広場
【遅牛早牛】 時事寸評「期待感から生まれた大勝利と現実とのギャップ 高市政権のこれから」
まえがき
[ それにしても2月8日の総選挙の結果はすさまじいものであった。それは現行選挙制度がいきなり牙をむいたようで恐ろしささえ感じられた。単独で3分の2を超える自民党の議席について、16日の朝日新聞朝刊は「内閣支持層でも『多すぎる』としたのが51%。自民支持層は44%が『多すぎる』と答えた。」と2月14, 15日に行った同社の全国世論調査の結果を伝えている。
今回は、総選挙の結果について簡単な計数的分析を行いながら、高市人気について考察し、さらに中道の課題や今後の政局についての見通しも掲載した。 とくに、現行選挙制度と奇襲解散が重なることによって驚くような結果が生みだされたことや、とりわけ存立危機事態と国会承認との関係におよぼす重大な影響についても指摘をしたもので、できれば選挙制度の改正を考えるべきであると思う。
全国的に寒さと雪害に苦しむ2月初旬であった。阪神間は降雨不足が悩ましい。筆者は近辺の酒蔵開きなどで掲載が遅れたこと(みっともないことで)を申しわけなく思っている。
なお、本稿は2月9日に時事ドットコムへリリースしたものを部分的に下敷きにしている。例によって文中一部敬称略、政党名は略称も併用。]
1.自民への回帰と高市人気で単独でも3分の2超え、与党で352議席
自民党316、維新36、与党で352という超ど級の大勝であった。それに比べて、にわか仕立ての中道改革連合(中道)の49議席はあまりにも惨めな敗北といわざるをえない。また国民28、参政15、みらい11、共産4、れいわ1、減税ゆう1、その他無所属4となった(保守と社民は0)。これらの議席には、自民党のいわゆる名簿不足分である14議席が中道6、維新2、国民2、みらい2、れいわ1、参政1が含まれている。この議席は譲渡されたということではなく自民党の立候補者がいなかったという理解のほうが適切であろう。そういえば、前回は国民民主党も3議席分名簿が不足していた。
さて、そこで小選挙区における得票率と獲得議席率(以下議席率)の関係を見ながら違った視点の解釈を提起してみようと思う。(以下票数は万単位、百分比は小数点以下1位に丸めている。)
自民党については、今回小選挙区では5645万票中2779万票を獲得し、249議席を得た。得票率は49.2%で獲得率は86.2%である。ちなみに2024年(石破氏)の総選挙では2087万票で132議席を、2021年(岸田氏)は2763万票で187議席であった。2024年は38.5%の得票率で47.8%の議席率を、また2021年は48.1%の得票率で67.5%の議席率を得ている。
着目すべきは、少数与党に陥落した2024年でさえ、2021年比で676万票の減であり、逆に大勝利となった今回の2026年では2024年比で692万票の増で、議席の増減感よりも票の動きのほうが少ない点である。つまり、得票数は約700万票の範囲で変動しており、議席数は187から132へさらに249へというように50~110議席の幅で増減している。ということは700万票(選挙区あたり2.4万票)で政権が入れかわるということで、無党(政党支持なし)派の投票動向が結果を左右しているといえる。
ただし、2024年→2026年では公明党の連立離脱による減票があったが、その程度は不明である。おそらく、その穴を埋めての700万票増であったから、1000万票を超える増票があったと思われる。その中の「高市だから」票がどの程度であるのかは実際のところ分からないのである。
【 投票率は56.26%で、前回の53.85%よりも2.4%ポイントほど高くなっている。投票総数は、小選挙区で51万票、比例代表選挙区(以下比例代表)で133万票増えている。ほぼ同数なのだが今回は80万票ほど比例代表のほうが多かった。理由は今のところ不明である。】
したがって、歴史的大勝利とはいえ小選挙区での得票率は49.2%と、わずかに過半数に達していない、にもかかわらず86.2%の小選挙区議席を獲得したのは、ひとえに現行選挙制度によるデフォルメ効果といえる。
また、比例代表(11ブロック合計)では5726万票のうち自民党と記載されたものは2103万票で得票率は36.7%であり、その配分議席数は81(議席率46.0%)であった。しかし、名簿登載者不足(立候補者なし)ということで他党へ14議席が割りふられたことから獲得議席が67に減じた。その議席率は38.1%で、これは得票率と近似している。議席配分に使われるドント方式にもデフォルメ効果がある。