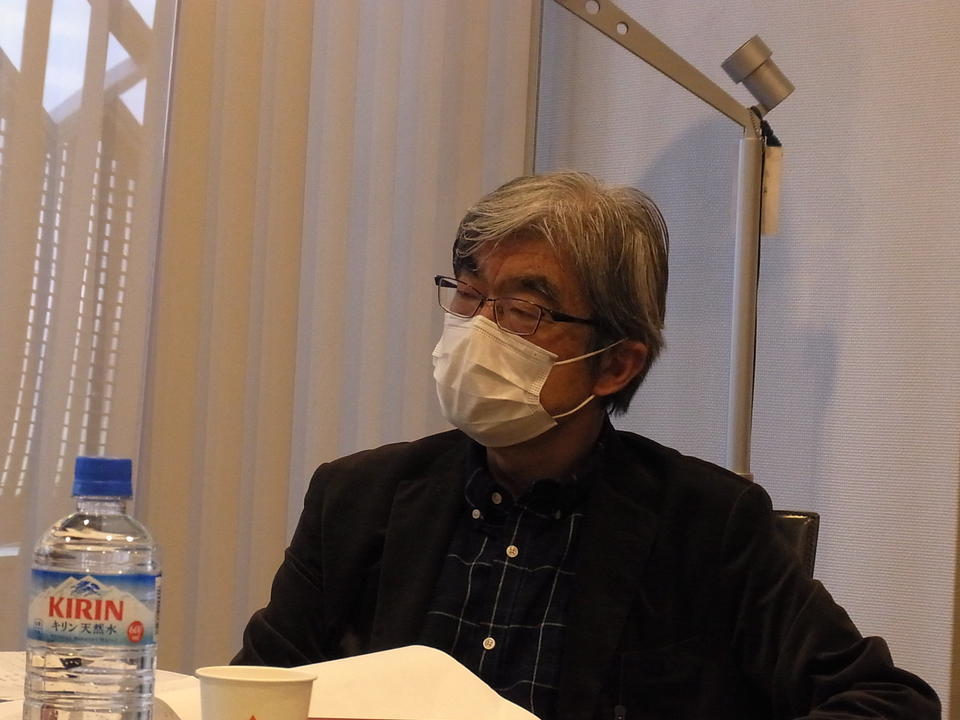研究会抄録
ウェブ鼎談シリーズ第(14回)「戦後の労働運動に学ぶ」
講師:仁田道夫氏、石原康則氏
場所:三菱電機労働組合応接室

【加藤】本日、お集まりいただきありがとうございます。まだまだコロナの猛威が衰えないということで、一日も早くワクチンの配給を待っているということであります。
【仁田】加藤さんは、対象年齢に入っていますから。
【加藤】前回は、第12回が戦前の労働運動に学ぶということで、いろいろお話を聞かせていただきましたし、意見交換も有意義であったと思います。引き続き、今度は戦後ということで、主には1945年から60年、このあたりまでを紐(ひも)解いていただき、その中から今日の、どういった形で、労働運動として、学ぶべきところは学び、新しく展開していくところは展開していくということだろうと思います。
労働学校あるいは研修会とかで、労働戦線統一ですから、1970年代後半から80年代、89年の現在の連合ができたあたりは私も話をする立場でやってきたわけです。しかし、そのベースとなっている戦後の労働運動の礎がつくられた時期にどういう流れがあったのか、あるいは歴史的な背景、あるいは当事者たちのいろいろな考え方、動きなどについて私自身がいまひとつ身についていないということで、戦前の話については、前回第12回で一区切りをつけたということで、戦後の労働運動のスタート地点における流れについて、今回クリアにできればいろいろな方々のお役にも立つのではないか。
ということで前回に引き続き、仁田先生、石原さん、お二人にお話をいただきたいと思います。主には仁田先生の方から、論点を絞っていただきまして、戦後の労働運動の話を概括していただきそのあと、石原さんの方から、質問も含めてあるいはいろいろな視点から問題提起をいただくということで、少し柔らかく意見交換ができればと思っております。まず、仁田先生よろしくお願いいたします。
第一部
【仁田】はい、今日の話は、UAゼンセン『コンパス』に掲載した「日本における労働運動の形成2」という論文が元になっています。これは前回もお話しましたけども、UAゼンセンの松井さんの依頼で、労働組合運動論のテキストを書こうという話になって、その第一章という位置づけです。まず、労働運動史がなくてはいけないだろうということになり、それを一章1万字で書くはずだったんですが、前半部分の戦前編が3万字になってしまった。後半部分の戦後編は、本当はもっと長くなるところだったのですが、内容を絞り込んで3万字にとどめました。扱っている時期は、だいたい1960年まで。それぐらいまでの時期に、日本の今日の労働組合運動の基本的なパターンができあがったと考えるからです。
労働運動史を書くときに、いろんな方法があります。代表的な本として、たとえば大河内・松尾の『日本労働組合物語』(筑摩書房)というシリーズがあります。これは、血わき肉おどる労働運動物語でして、日本の労働者かく闘えり、みたいな話が半分ぐらいを占めています。個別争議を扱っていると、とてもコンパクトに書くことはできないので、この際は、どのように労働組合の組織ができてきたのかを主な視点として、労働運動史をおさらいしてみようということにしました。
労働組合役員、活動家のみなさんに役立つ労働組合論の教科書を書こうということでありますので、どう組織をつくるのかが、労働組合にとって、やはり出発点であり、キモでもあると考えます。労働組合期成会を組織した高野房太郎のスローガンに、「結合は勢力なり」とあります。なるべく大勢の労働者を、一つの組織に結集して、それが強固な団結をすることによって発言力をつくる。それを使って、自分たちの生活改善をし、社会を改革していく。どう結合し、どう勢力をつくるのかを視点にして書いてみようと考えました。戦前は、前回、話しましたけれども、海員組合のような例外を除けば、基本的には、政府と使用者が非常に頑迷であったために、労働組合をつくる動きはあったけれども、先進国並みに組織を確立することはできなかったということになります。
それだけではなくて、戦時期には、ほそぼそと組織されていた労働組合も解散させられて、いったんゼロになっていました。そこから、戦後、労働組合が、新たに立ち上がって、自前の運動をおこなえるようになっていったわけですが、そのプロセスをどのようにとらえるかが、戦後編の課題です。まず、大きく時期を二つに分けています。これは、常識的な見方だと思いますが、第一が1945年からだいたい50年ぐらいまでの戦後改革の時代、これを、戦前からのつながりで、第三期組織化運動の時代ととらえます。この時期の労働組合運動を、私は戦後直後型労働組合運動と呼んでおりますが、今日の労働組合運動とかなり違うものだった。そして、第二の時期が1951年、直接的には総評ができたことをきっかけとして、1960年くらいまで。これを第四期組織化運動の時期と規定しました。この期間に日本の労働組合が再編成され、その結果、企業別組合を基礎として、産業別組織がその上にあり、それをナショナルセンターが統括していく、そういう基本的な体制が確立したといえます。
今日につながる労働組合の姿は、第三期から第四期にかけてつくり出されたものだったと考えられるので、それがどう達成されたのか、違うやりかたはなかったのかということを含めて考えてみたい。戦後直後の時期は、いきなり労働組合がパッとできてしまって星雲状態なわけですので、それがどういうものとして発展していくか、いろいろな可能性があっただろうと思えるんです。一面では、どこに行っちゃうか分からない。極端な話、ぜんぶ御用組合になったかも知れない。いろいろな可能性があったけれど、結果的には、第四期に至って今日の労働組合の元になるようなものができあがってきた。それが何か必然的な道筋だったととらえるよりは、いろいろな可能性があり得たなかで、当事者がある道を選んで進んだ結果、今日の姿に落ち着いたのじゃないかという見方を追求しながら、振り返ってみたい。
戦後の労働運動史について、たくさんの書物や論文が書かれ、いまさら議論の余地はないように思えるのですが、実際は、議論がなされていないテーマがたくさんあり、私は研究不足だと考えています。そうなってきた原因の一つは、言葉は適切じゃないかもしれないけれど、知識人の間に左翼的偏向みたいなものがあったことではないかと思います。そうした偏りから自由になって問題を設定し、議論をしてみようと考えて、この論文では、戦後労働運動のリーダーの一人だった滝田実さんの問題提起を出発点として、議論を進めてみたわけです。テーマ自体は、言い古されたもので、「なぜ、企業別組合が組織の中心となるような組織体制になったのか」です。学者は、労働市場の構造とか、戦時体制の影響とか、客観的背景に着目して議論してきたわけですが、滝田さんは、企業別組合の幹部から出て、全繊同盟のリーダーになり、この組織をいかにして立派な産別組合にするかという課題を立てて、苦労した人です。だから、主体的観点から、もうちょっと、この産別の力が強くなるように最初から取り組まれていれば、こんなに苦労しなくても済んだのに、という強い気持ちが感じられる問題提起です。
その一つは、占領政策についての疑問です。占領政策が、戦後の労働組合の広がりに大きな影響をもったことは、だれもが認めることです。滝田さんは、占領政策で、どうして産業別組合をつくれと言わなかったのか、そっちの方に誘導しなかったのかという設問を提出しているんです。もちろん、面と向かってそう質問していたら、衝にあったアメリカ人に、自分の国の労働運動なんだから、自分たちで考えるのがあたりまえだろうと言い返されてしまったかも知れません。初代GHQ労働課長だったカルピンスキーは、そういう気持ちだったのじゃないかと思います。ただ、戦後改革で労使関係政策に介入した以上は、介入ついでに、徹底的に、正しくやってほしかったという当事者の気分は分からんではない。
1945年の暮れに、労働組合法ができますが、これは、必ずしも、GHQの指令ではなかったみたいなのです。じゃ、だれが主導してつくったんだということになると、実は謎のところもあります。旧内務官僚が主導したのかも知れない。労働運動側は、労働組合法をつくってくれと、昔から言っていたわけなので、西尾や松岡は、戦後、労働組合を発足させるときには、ちゃんとした法の支えを作ってもらわないと、日本で労働組合組織化が進むようにはならないだろうと思っていたでしょう。使用者が何をするかわからないので、それを縛りたい。官憲が労働運動弾圧をしない保証が必要だ。カルビンスキー労働課長に、労働組合関係者だか、官庁担当者だかが労働組合法をつくりたいと相談に行ったら、法律なんかつくると、しばられて面倒だぞと言われたという話が残っています。
それはまあ、そう言えなくもない。勝手につくって、これを認めてくれという方が、運動側にとって楽じゃないかとも考えられる。いや、そう言われましてもといった感じで、やっぱり、法律がないと安心して運動ができませんというようなことで、労働組合法をつくることになった。まあ、日本の労働者が、あんなに労働組合をつくるとは、みんな思ってなかったんじゃないか。総同盟の人たちも、労働官僚たちも。GHQがどう思っていたかは分からない。ところが、その号令が発せられたら、日本の労働者が、「ワーッ」と、組合に飛びついちゃった。まさか一年でこんなでっかい組織ができちゃうなんて、だれも想像してなかったと思う。労働組合法を施行しなくてはならない厚生省労政局の官僚が、大蔵省と予算折衝して、主計局主査に一体組合がいくつできるんだと問われて、そんなもの分からないと思いつつ、一年くらいで2000くらいになるんじゃないかといい加減な数字を立てて予算を組んだと回顧しています(全国労働委員会連絡協議会事務局編『労働委員会の二十年―回顧と展望』全国労働委員会連絡協議会、1966年:233ページ、中西実の発言)。実際には、1946年6月末には12000組合368万人が組織されてしまった。
ジョン・ダワーの『敗北を抱きしめて』(岩波書店、2001年:原題はEmbracing Defeat)という本があります。アメリカ軍は抵抗する日本人に出会うと思って、身構えて乗り込んできたんだけれども、日本人は、何の抵抗もなく、占領軍の改革政策を進んで受け入れてしまった。労働組合の場合もそうでした。もちろん、最初は「戦後編」に紹介した小泉製麻のケースのように、恐る恐る始めているところもいっぱいあったでしょう。でも、本当に短期間に、労働組合ってものがあるらしい、何かいいものらしいとか、マッカーサーもつくれと言っているらしいというような情報が広がって、アッと言う間に、バスに乗り遅れるな、みたいな感じで、労働組合結成に走ってしまった。だから、労働組合法をつくって、基本的なガイドラインをつくっておくことは必要だったんじゃないか。逆にいうと、法律があれば、みんなが安心して組合をつくれる。
法律を制定するときに、占領軍のカルビンスキーは、労働組合法を、どういうふうにしろとあまり言わなかった。せいぜい言ったのが、あまり取締りし過ぎじゃないのかとか、目的規定に団体交渉権が入っていなかったので、入れろと言ったとか。基本的には日本側主導で、西尾や松岡の運動側の考えを動力にしながら、末弘先生と旧社会局官僚の合作で新しい労働組合法ができるという経緯をたどったと思います。末弘先生は、自由度の高い労働組合法をつくりましたと言っています。一面自由なのはよいけれど、もうちょっと、こういう労働組合でなければ、労働組合とはいえないという条項を明確にしておくことは考えられたのじゃないか。滝田さんの考えを敷衍していくと、そういうことになる。
アメリカでは、ニューディールの初期に、労働組合組織化を促進する法律を作ったのですが、カンパニー・ユニオンが、いっぱいできちゃっていた。それをぶっ潰す必要がある。多分CIO(産業別組織化委員会、のち産業別組合会議)が要求して、このままではだめだということになった。どうやって潰すか考えたときに、民主主義の国柄だから、労働者が公正な選挙で投票して、組合を選ぶ(組織しないことを含めて)。その選挙も、勝手にやらしてはだめで、NLRB(全国労働関係委員会)が、ちゃんと投票箱を管理し、選挙のプロセスも監視して、正しい選挙運動でやっているかどうかをチェックする。経営者が働き掛けてはいけない、ひじょうに厳格です。そういうワグナー法のやり方によって、従業員代表制の裏返しのようなカンパニー・ユニオンにいっちゃうのを止めようとした。現に組織されていたカンパニー・ユニオンをNLRBが無効にしたりした。労働者が公正な手続きで、自分たちで選んだ労働組合でないとだめだと。その中で、実は、労働運動のなかで、CIOとAFL(アメリカ労働総同盟)が対立していたわけなんだけど、ルーズベルト政権はCIOを応援しようとしたように見えます。どうやって応援したかというと、交渉単位、労働組合をつくる組織の単位を、NLRBが認定するときに工場一本にすることが多かった。AFLはもともと熟練工組合だから、職種別に組合をつくらしてくれと希望したのだけど(機械工とか、あるいは、保全・工作部門とか、そういう単位で)NLRBは、そうではなく工場一本にして、その中での多数決をとった。同じ工場でもホワイトカラーは、さすがに交渉単位を別につくったみたいだけど。この結果、AFLのほうも、工場別支部を基礎とする産業別組織に転換していくことになります。
ワグナー法は、カンパニー・ユニオンを否定して、産業別の労働組合が職場をおさえて、それで強い統制力をもった労働組合をつくるというのが政策目標だった。ただ実際には、アメリカでそれが確立したのは、ワグナー法だけではだめだった。戦争になって、War Labor Board(戦時労働委員会)という仲裁機関ができます。そのもとで、戦時体制の労使平和を維持しようとした。組合にとって、一番重要だったのは、ユニオン・ショップを認めてもらうことでした。アメリカの労働者は実利的だから、ユニオン・ショップ協定がないと、フリーライダーばかりになっちゃう。「賃金があがるのはいいね。がんばってね。でも、ぼく、組合費は払いたくないんだけど」、そういう人ばかりになっちゃうと、労働組合組織が維持できなくなってしまう。一方で、ユニオン・ショップは、組織加入を強制するわけだから、アメリカの個人の自由の観点からみると、ひじょうに難しい問題がある。今でもそれをめぐって、争いがあるんだけども、それを、組合に協力してもらって、ストライキしないで、戦時体制を安定させるために、これ認めてやってくれというような話になって、結局、政府の介入によって、産業別労働組合ができあがった。これは、アメリカの例です。
ドイツ・モデルというのは、例えばドイツに行って、三菱電機がジーメンスを買収して、三菱ジーメンス労働組合をつくりたいと言っても、たぶん認めてもらえない。ドイツでは、労働協約法が重要です。労働協約法に、協約締結能力を認める前提として、いくつかの条件が定めれらている。そのうち、いちばん重要な項目は、Sozial Maechtigkeitです。社会的実力と訳されているみたいですが、Machtは力ですね。それがある。どんな組合が力があると認められるかというと、大きいというのがまずある。大勢を組織しないとダメ。さらにいえば、産業全体を組織しているとか、そういう労働組合でないと、協約締結能力があると認められない。ある職場や企業の労働者が労働組合を勝手につくって、協約締結権を認めて下さいといっても、裁判所は認めてくれない。協約締結能力を認められない労働組合が使用者に団体交渉に応じて下さいといっても、応じてもらえない。こういう条件、こういう組織形態、これだけの規模で組織していなきゃならないといった基準がある。この制度は、今、少数組合や、職業別組合みたいなものが出てきて、法律上問題になっているようだけれど、だからといって、協約締結能力という考え方を、ドイツがすべて止めちゃうかというと、そういうことにはならない。
これはドイツ風の労働組合に対するしばりで、だから、国によっていろいろ違う。イギリスのように、そういうことにはあまりしばらない、勝手にやれという、そういう国ももちろんある。どちらかというと、何か基準があって、こういうのを労働組合とするというのが、多数なんじゃないか。
だけど日本は、労働組合法で、管理監督の地位にある者をメンバーにしていると、法内組合ではないから、不当労働行為制度による保護を受けられないとか、一定の条件は定められているけれど、基本は、何でもいい、好きなようにつくりなさいということになっている。2人でも労働組合はつくれる。
もう一つの滝田さんの仮説は、労働組合をつくった労働者たちは、組合のあるべき姿について何も知らなかった。だから、リーダーたちが、労働組合というのは産業別につくるもんだよ、世界中そうやっているよと言えば、みんなそれにしたがったんじゃないか。どうしてそうならなかったのか。占領政策が欠落したところを、労働組合組織者たちが補えばよかったのじゃないか。
総同盟も産別会議も、産別組織を志向していたのは確かです。総同盟はもともと、そういう立場だった。産別会議ないし共産党の方は、あまり労働組合運動の経験のない組織だけれど、産別でいくという総同盟の方針を自分たちも採用した。ただ、総同盟と一緒にやるのではなくて、共産党の指揮下の組織として労働組合を取り込みたいというのが、徳田球一の目論見だったんじゃないか。
産別会議ができてくるプロセスを見ると、新聞単一というのがいちばん最初の産別組織で、46年2月にできている。自分たちでまず、産別組織をつくった。かならずしも共産党の方針とはいえない。その時点では、産別会議をつくる方針も確立していなかった。聴濤克巳というのが朝日新聞出身で、新聞単一の委員長になって、そのあと、産別会議の議長になるんだけど、彼は、最初は共産党員ではなかったというんですね。読売争議の中心メンバーの一人だった増山太助がそう証言しています。もちろん、産別会議の議長に就任するときは、共産党員になっていた。読売の組合は、その前に、第一次読売争議をやっているから、共産党の主導権が確立している。読売の組合長だった鈴木東民も、共産党員だった。鈴木は、当然、自分が新聞単一の委員長になり、産別会議の議長になると、そう思っていたようだけど、徳田は、聴濤克巳の朝日をつかまえないと、新聞単一をとりこむことはできないから、聴濤を委員長にしてやれというふうにして鈴木をおさえたというんですね。ともかく新聞産業では、格好だけは立派な産別組織ができた。
読売新聞従組ができて、ほかの新聞社でも、企業別組合がボロボロできていく。それが集まって、新聞単一という産別をつくった。単一だから、新聞単一労組が単組で、その下に支部がある。朝日支部、読売支部、毎日支部と、そういう組織に変えた。形式上は、新聞単一が単位組合で、下の支部をコントロールしている。そういう姿・形は立派な産別組織だけど、実際は、統制力がない。すぐに馬脚があらわれる。
結成半年後の1946年10月闘争で、新聞単一がゼネストをやるということになった。すべての新聞を止める(NHKの組合も放送支部で同時に放送を止める)ということを決めた。なぜこういう闘争をするかというと、その前に、読売新聞で組合長以下幹部が全部解雇されるという事件があって、組織が分裂してしまった。刷新派という第二組合の人たちが出てきて多数派になっちゃった。だけど、新聞単一は、刷新派のひとたちを否認して、少数の解雇された人たちを中心とする左派の組合を、あくまで新聞単一の組合だといい張った。そして、こういう人たちの首を守るために同情ストやるという機関決定をした。だけど、スト直前になって、朝日落ち、毎日落ち、読売はもちろんダメ。だから、大手の新聞各社は全部落ちた。地方の新聞は、やったところもある。放送支部もストに突入した。ラジオ放送が止まったらクーデーターになっちゃうから、組合を排除し、政府が介入して、ラジオ放送は続けたという話なんだけど。新聞単一は、企業別支部を統制できてないわけだ。
当時の実情からすれば、新聞を止めるなんてとんでもない話で、ラジオと新聞くらいしかマスメディアがない状態で今日は新聞出ませんといったら、情報遮断になってしまう。読者に何を言われるか分からない。だから、下からの突き上げをくって、ゼネストを実行することができなかった。形は産別組織なんだけど、実際は企業別支部の統制ができない。ちゃんと産別としての組織を整えて、下部組織をコントロールして、組合員を教育し、この際、読売のために、同情ストやるのは新聞業界に働く者の労働組合としては絶対必要なんだとみんなに納得してもらって、ストに入ろうというように運動しなければいけなかった。しかし、そういうことができずに、号令さえかければ、同情ストができると勘違いしたとしか思えない。まあ、経験がなかったから、仕方ないかも知れないけど、結局、その程度の組織だったと考えざるをえない。
産別会議は、多くの傘下組織を単一と書いているけれど、一方は、新聞単一のような事実上の企業別組合の連合体で、他方、官公労は、企業別組合イコール産別組合で、国鉄、全逓など。それから官公労ではないけど、やはり企業別組合イコール産業別組合だった、全日通とか。
唯一、民間企業を複数組織して、産別単一組織の実態を確立したのは、電産です。この電産にも特殊事情があった。そのころの電力業界は、戦時期の電力国家管理が続いていて、発電は日本発送電という特殊会社が一手に引き受ける。そこでおこした電気を、地域別の配電会社に流して、各家庭へは、その配電会社が流す。配電会社は9つあって、それぞれに企業別組合ができているから、最初は日本発送電の組合含めて10組合の集まりだった。
それをまとめていくために、最初は協議会をつくる。慎重だった。電産協が、1946年10月闘争をやって、その経験を踏まえて、47年になってから単一組織にする。それが電産労働組合で、企業別組合は支部になった。そして、産別組織が組合費なんかもちゃんと取る。ほかの産別組織とはレベルが違うんですよ。論文には、組合費をいくらいくらにして、そのうち、30%を本部に集めたとか、細々したことを書いてあります。こういうことは、今までの運動史には、ほとんど出てこない。本当は、さらに、歩留まりはいくらだったか、サバ読みはどれくらいやっていたかとか知りたいけれど、記録がない。だから、研究者も研究しない。だけど、労働組合の組織をちゃんとつくろうと考えると、財政がキチンとしているかどうかは決定的だから、それを調べなくてはいけないはずだ。そもそも、日本の労働組合の財政はあまり公開しない習慣で、大会に行っても、経過報告はもらえるけれど、財政報告はもらえません。
産別会議の財政がどうなっていたのか、研究を見たことはないですが、規約を読むと、完納できなかった場合は、執行委員会にかけて対応を決めると書いてある。こんなこと書いてはだめだ。みんな完納しなくても言い訳すれば大丈夫となるに決まっている。
総同盟は、戦前以来の伝統があって、そこはうるさい。松岡駒吉などは、戦前総同盟で会計担当を兼ねていて、お金にうるさいので有名だった。それでも、戦後総同盟結成時に、加盟人員が85万人いるというのは水増しで、ちゃんと組合費を払っていたのは、ずっと少なかったと言われています。
産別会議の方は、データはないけれど、もっとひどかったのに決まっています。組織運営のルールも明確でなく、組合費をまともに集められない組織で、どうしてあのような大闘争ができたんですかということになりますが、一つには組合費がなくても活動ができる時代だった。つまり、ヤミ専がヤミでなく、自由に何人でも、組合役員を専従にできた。経営を、労働組合が占拠している状態だから、何十人と専従がおける。会社のお金で労働運動をやっている、それが常識になっている時代だった。
だから、『戦後労働組合の実態』(東京大学社会科学研究所)という最初の単位組合調査報告をみると、それがはっきり出てきます。予算の中に、人件費というのがほとんどない。多いのは旅費とか。そんな中から、産別や連合組織の役員も在籍で出ているから、一所懸命みんなから組合費を集めなくても、運動ができた。
総同盟はそうではなくて、一人一円と言っているけど、お金が大事だということが、よく分かっていて、組合費をきちっと集めて、それでもって組織を運営していこうと言っている。そのうちどれだけを産別や県連に収めるとか決めている。ところが、論文の中にちょっと書いたけれど、荒畑寒村『寒村自伝』によれば、共産党の方は、組合費、安いよ、安いよといって、1人10銭で大丈夫だからとかいって、企業別組合を集めている。でも、それだったら、労働組合は、自前の金がなく、自前の専従もいず、しっかりした組織ができない。なのに、どうして産別会議が運動できるんですかということになるんだけど、それは共産党があるから大丈夫だというのが、徳田球一の路線なんです。実際、産別会議傘下の組合だけでなく、総同盟系や中立の組合にも、共産党の組織がびっしり網の目がはっていた。最初、共産党の党員は1000人ぐらいしかいなかった、1945年12月に開いた第4回党大会時点では。それをねずみ算式に増やしていった。1000人の党員というのは、相当な数です。そのころ、社会党はどれくらい党員がいたんだろうか。そんなに大勢いなかったのじゃないか。
戦前の共産党員は、ちょっとビラまきしたら牢屋にぶち込まれて、5~6年は入っている。転向して、出てくる者もいたけど、非転向でがんばっている者もいた。戦後産別会議で書記局員になり、その後労働評論家として多くの本を書いた齋藤一郎は転向せず、牢屋に入っていた。そういう筋金が入っているみたいな人は、けっこういた。しかし、大衆運動の経験はあまりなかった。徳田球一だって、1928年の共産党員一斉取り締まり(3・15事件と通称されている)で捕まって、占領軍に解放されるまで、ずっと牢屋の中にいたわけだ。それで「獄中十八年」ということになる。彼自身は、労働運動の経験はほとんどない。あのころの共産党で、労働運動の経験があって、大衆運動のリーダーになれた人としては、渡辺政之輔が代表的だけれど、殺されてしまった。共産党系の労働運動組織である評議会で、中心になって活躍していた人は、転向組が多い。労働運動家として優秀だったのは、三田村四郎とか、鍋山貞親とかだと思うけれど、転向して、戦後も共産党に戻らなかった。獄中十八年で残った人たちは、志操堅固だったけれど、大衆運動のリーダーとしては、ちょっと今一だったんじゃないか。
総同盟が「産業別が一番いい」と一所懸命働きかけても、ちゃんとした産業別組織をつくれない。全繊だって、連合体で行くしかないということになった。ナショナルセンターが分裂していると、組織競争が起こるから、自分のところだけ、ちゃんと組合費を集めて、きちんとした産業別組織をつくろうとしても、相手が安上がりの粗製乱造で、さあいらっしゃいとやっている状況では、なかなかできない。だからこの時期に、ちゃんとした産業別組織をつくるのはひじょうに難しかった。結局、官公労の企業別組合イコール産業別組織というところを中心に運動をやることになった。
この時期、民間で、上に述べた電産の特殊例を除くと、産業別組織として、とにもかくにも産業全体を組織することができたのはただ二つです。一つは全繊。これは要するに、総同盟の松岡駒吉が大手の会社を全部回って組織した。それでも、最初は、鐘紡とか、大手でも、別の組織をつくっていたグループもあったのを、何とか全繊同盟に入れて、勢ぞろいに成功するという経緯だった。
もう一つは、総同盟にも産別にも入らなかったんだけど、私鉄総連。私鉄総連には、戦前、中間派の労働運動家から、共産党に行った津脇喜代男(初代書記長)がいて、彼のリーダーシップが大きかったと思うけど、私鉄総連は、総同盟にも産別にも入らない、両方が合併したら、そのとき、そこに入るという建前で、断固として中立を守っていた。でないと、共産党系と非共産党系の勢力が半々だったから、組織が割れちゃう。津脇という人は、戦前の非転向共産党員で、戦後も早くから共産党員なのだけれど、徳田の組織路線に従わなかったことになります。徳田は、共産党系の組合だけ集めて産別系の産業別組織をつくれという路線だったから。
だけど、私鉄総連は、労働組合は統一していかなければならないといって、どうやったのかはよく分からないけれど、徳田球一を説得して、中立組織として私鉄総連をつくっちゃった。これは私鉄総連が企業別組合を集めて、集合体をつくるやり方だけど、とにもかくにも全国の主要な私鉄の労働組合を集めて、一つの組織にした。その後、分裂も起こしていません。1947年にできた組織を、そのまま今日まで継続しています。
電機でいうと、産別会議系は、東芝と日立で、日立総連は、組織として産別会議系の産別組織に入っていたわけではないようだが、三分の二くらいは、産別系の組織の下にあった。東芝の組合は、46年十月闘争とか産別会議の運動で先頭に立って活躍していた。三菱電機の組合は、余りまじめに産別と付き合わない感じだった。関西系の組合だったから、あまり巻き込まれないですんだのでしょうか。電機は、そういう具合で、産業別組織としてまとまっていなかった。
鉄も、まとまらない。日本鋼管なんて、川崎製鉄所労組は総同盟の拠点組合、鶴見製鉄所労組は産別会議の拠点組合、一つの企業の中だって割れている。だけど、賃金交渉しようとしたら、会社としないといけない。だから、川崎製鉄所の組合と鶴見製鉄所の組合と一緒になって交渉しなければいけなかったはずです。まあ製鉄所は、単体で結構大きいし、事業所レベルで動かせるお金もあったかもしれないから、それなりに単組の運動ができたのかも知れませんが。でも、こういう組織状況で、産業別統一闘争ができるかといったら、できない。
こんな組織の状態で、どうしてあんなに激しい運動ができたのか。いろいろ要因があるでしょう。ハイパーインフレだったからね。とにかく賃金をあげてほしい、それから統制経済だったので、国の賃金統制政策がターゲットになりやすかった。公務員がその中心になります。滝田さんの問題提起に対しては、結局いろいろな事情で難しかったから、企業別組合中心にまとまっていって、それをどれだけ産業別組織が束ねて、強団結させて、統一闘争を行っていくか、というふうにするしかないというのが、その後の第四期の運動の結論になっていくわけです。
だから、そのときになると、もう組織はできあがっているし、それに応じた法律もできあがっているから、それを抜本的に変えるのは非常に難しい。結局、今言ったように、そういう基本的構造を前提にして、その中でもできることはあるでしょうという話にならざるを得ない。だけど戦後直後の時期というのは、政策のありようや、運動の進め方によっては、全然違う組織体制ができたかもしれない。流動的な時期だったのだと思います。
石原さんの問題提起ですが、なぜ占領軍は総同盟が嫌いで、当初共産党・産別会議を一所懸命応援したのか、これはちょっと謎です。最初、CIO系ないし過激なニューディーラーが多かったせいだろうとか、その中には共産党員もいただろうとか、いろんな説があるけれど、憶測ばかりで、確たる証拠に基づいた議論はないです。私は最近になって、獄中共産党が1945年10月に出獄した際に出した声明「人民に訴う」を初めてまじめに読んだのです。なかなか面白い文章だと思いました。私が注目したのは、その中に、「団体交渉権」という言葉が出てくることです。「人民に訴う」というのは、今までぼくらが教わった一般的な話では、戦前コミンテルンの32年テーゼの焼き直しであって、牢屋に入っていた共産党員たちは、世の中のことが分かっておらず、昔の頭ででてきて活動したから、情勢にピントがあっていなかったのだというようなことでした。けれども「人民に訴う」には、32年テーゼにも、その前の27年テーゼにも出てきていなかった「団体交渉権」という言葉が入っている。彼らはワグナー法を知っていたのだろうか。そんな知恵を、どこで仕入れたんだろうと思うくらいです。天皇制だけは廃棄するけど、共産党が政権を取る、少なくとも権力側に入って民主主義の革命をする。裏では2段階革命論だから、一旦権力を握れば、社会主義革命に乗り出すということを想定しているわけだけど、それは一切言わないで、第一段階の民主化の話で一貫している。これを読んだ占領軍が共産党を味方だと思ったということなのじゃないか。もちろん、天皇制をどうするかなどの戦略課題について、共産党の言うことを聞くつもりはなかったと思うけど。占領軍で来た人たちの当初の思い込みでは、日本人は、特攻隊にみられるように、天皇陛下万歳で凝り固まっているから、民主化しろなどと言っても容易なことではないと思っていた。無理からぬことだと思うけど。イラクに乗り込むアメリカ軍と一緒みたいな感じでしょう。だから、ゲリラが起こるのではないかと心配してきたと思う。だけど、ゲリラ闘争をやるようなのはいなかった。むしろ、ダワーの本にあるように、「民主化、ハイ、それいいですね」、「大賛成です」とか言って、みんなそれに飛びついてくる。
1945年10月の時点では、日本人に民主主義を担わせるのはたいへんなことだと思っていたに違いありません。日本にだって、戦前、大正デモクラシーとかあったのだけれどね。だから、民主化のエージェントとして、労働者は労働組合に組織化し、農民には土地を分配し、女性には選挙権を与えて民主主義の支持者に育てようと考えてやっていたのでしょう。そのときに共産党曰く、「みんな信用ならないよ」と。「人民に訴う」にそう書いてある。資本家たちは頑迷固陋で、戦争犯罪者だ。役人、政治家は、みんな戦争に加担した者ばかりだ。総同盟・社会党は、これも戦争加担者の集団だ。だから、みんな信用ならない。この連中を頼りに民主化しようとしたって、うまくいくはずがない。そこにいくと、わが共産党だけは、常に天皇制には反対だし、戦争には反対だし、唯一、手が汚れていない政治集団だ。だから、日本社会を民主化するというなら、共産党をつかうしかないでしょうと。そこに「団体交渉権」なんて言葉もさりげなく入っているから、占領軍としては、共産党をつかって日本社会を民主化するというのは、アリじゃないのと思ったとしても無理からぬところがある。だから、最初は、共産党を大いに応援して、総同盟や社会党に対しては信用ならないみたいな態度をとる。筋金入りの労働組合主義者である松岡駒吉なんかは、嫌われている。少なくとも最初の2年間ぐらいは、こういう対応を続けていた。
共産党の方も、いかに占領軍を利用して自分達の勢力を伸ばすかを一生懸命追求した。占領軍は解放軍だと規定したといって、左翼評論家が後知恵で批判しているけれど、絶対権力者である占領軍を無理やり解放軍にしなければ、革命なんかできないわけだから、当然のマヌーバーでしょう。とにかく、占領軍はおれたちの味方だ。おれたちの後ろには、マッカーサーがいるぞ。そういって事大主義的な日本の大衆を、ひきつけて運動展開する。これを、巧妙かつ全面的にやったわけです。ある意味でそれがうまくいきすぎて、占領軍は、共産党は、どうも信用ならないと考えるようになっていったのでしょう。
一方では、別に共産党に頼らなくても、日本の人民は、どんどん民主化になびいている。天皇は人間宣言しちゃうし、日本人はすごく適応能力が高い。民主主義もマネするのが上手みたいだ。だからそんなに心配しなくても大丈夫だ。どんどん民主化して占領政策を推進していくことができるじゃないか。むしろ、邪魔になるのが過激行動をとる共産党だという話にかわっていった。
それから、「戦後労使関係史余滴21・団体交渉権について(その2)」(『中央労働時報』2020年11月号)に書きましたが、共産党のほうも途中で方針が変わったんじゃないか。上で指摘したように「人民に訴う」のときは、「団体交渉権」が入っていた。ところが、一年もたたない46年夏に、産別会議をつくるときは、団体交渉権はこっそりしまいこんで、経営参加というか経営権獲得の方向に転換した。もちろん、その間に、生産管理闘争をやったりして、勢いがついているということはあったと思うけれど、団体交渉権なんか、まるきりお蔵入りさせちゃっているわけです。言ってたことと、やっていることが違うじゃないとGHQ労働課なんかは思ったのじゃないか。
産別会議の規約をつくるときに、GHQ労働課が、いろんな資料を集めてやった。世界労連の規約や、CIOの規約をみせたりしてる。それにしたがって、細谷松太たちが規約案をつくった。ところが、徳田球一が、これはダメと言って、共産党本部が好むような、労働組合の自主性を弱めて、組織・財政の確立を妨げる方向で、規約案を修正させてしまった。目的規定からは、団体交渉権が落とされてしまった。これまでの左翼風の運動史だと、占領軍は、最初、正しい、民主的な政策をとっていたのに、その後、冷戦になったために左翼を弾圧する立場に変わったから、日本の労働運動がだめになったのだという筋書きになっている。だけど、それは、一面的で、共産党の自己弁護の主張だ。自分たちの主観からみればそうなるのかもしれないが、実際はそればかりではなく、共産党が情勢に流されて、変わっていったことも言わなければだめでしょう。
占領軍が、共産党をとんでもないやつだと思ったきっかけは二つあると思います。第一回は、1946年の5月19日に、食糧メーデーというのがあった。食糧メーデーというのは、単に食い物がないから、何とかしてくれという運動だと、なんとなくみんな思っているけど、そうじゃない。革命運動です。つまり、4月10日に戦後第一回の総選挙があって、いろいろいきさつはあったけど、自由党・進歩党の保守二党が吉田茂首班で連立内閣を組織しようと、首相官邸でやっていたら、そこに徳田球一に率いられたデモ隊が、なだれ込んで占拠して、政権樹立活動をさせないようにした。政権ができない。共産党は、選挙後の政権協議で人民共和政府をつくれと言っていたが、これは、基本、社会党と共産党の少数内閣をつくらせろという話だった。さすがに自分たちだけとは言わなかった。共産党は5人しか当選しなかったから。社会党は93人当選した。社共合わせても、474人中98人に過ぎない。たったの20%だ。保守2党が連立すれば、とりあえず247人で過半数をクリアする。しかし、占領軍が最大政党となった自由党の総裁鳩山一郎を戦前の発言を理由にして軍国主義者としてパージするなどという介入をしたものだから、共産党は、占領軍が保守党政権はだめだと言ってくれると期待したのじゃないか。少数人民共和政府でも認めてくれると思った可能性がある。もし、徳田の要求通りになったら、これは革命です。選挙の結果とかかわりなく政権ができる。それを大衆行動で実現しようとしたわけだから。
これに対して、マッカーサーが20日になって声明を出し、「秩序なき暴力行為」は許容しないと断言したので、官邸を占拠していた食糧メーデーの一団は、ただちに退去し、デモも中止してしまった。共産党は、このマッカーサーの声明にびっくりしたといいます。おれたちのやることは、当然、マッカーサーに支持してもらえるはずだと思い込んでやっていた。「人民に訴う」に占領軍が同意していると考えていたわけでしょう。
それに、共産党主導の「秩序なき暴力行為」は、それまでにも、実績があって、占領軍のおとがめはとくになかった。選挙直前の4月7日に開いた幣原内閣倒閣人民大会のあと、参加者数万人が首相官邸にデモ行進し、群衆は官邸の正門を乗り越えて構内に乱入した。警備陣は何をしていたのかと思われますが、たった300人の警官しかいなかった。デモ隊に圧倒されてしまうのは、当然です。追い詰められた警官隊は、ピストルを発射したけれど、群衆は引かないので、仕方なく米軍が装甲車6台、ジープ6台を出してようやく退去させた。5月12日には、世田谷区の米よこせ闘争の区民大会代表100人余が皇居内に赤旗をかつぎこんで、応対した宮内省の課長に宮城内の隠匿米解放の要求をつきつけています。
占領軍が内部でどういう情勢分析をして、こうした「秩序なき暴力行為」に対処しようとしていたのかは分かりませんが、5月20日の声明で、はっきりと態度に示した。結局、選挙の結果は尊重するというGHQの意向があったと思います。選挙はしたけれど、反動的な保守候補が多数選ばれてきたから、その結果を否認して、共産党の希望する少数内閣を作らせるなどということはできない。アメリカは民主主義の国だから、選挙結果をまったく無視して、政権をつくるなんていうのはあり得ない。
二回目は、2・1スト。約1年後の事件です。1947年2月1日、これは、街頭行動ではなくて、公務員の賃金闘争をきっかけとして、全国無期限ゼネストを宣言した。国鉄や電力も全部止まるわけだから、そんなことやられたら社会がマヒしてしまう。それをやめてもらうために、政権がほしいというなら、政権をあげようかと、言ってもらえるのではないか、占領軍も、それを認めてくれるだろうと思っていたとしか思えない。だけど、占領軍は、選挙によらない政権を認めるつもりは毛頭ない。それを、大衆運動を背景に画策して、政権をとろうとしている共産党というのは、信用できないということになったのじゃないか。
この2回目の政権奪取トライについても伏線があって、占領軍の対応が共産党を誤解させたということがあるのじゃないかと思われます。もともと占領下日本には、無制限に自由な争議権はなかった。占領目的違反の争議はできないというのが大前提です。たとえば、占領軍の物資輸送を妨害するようなストライキはできない。だから、コーエン労働課長は、国鉄のストライキはダメだよというように徳田に言っていた(コーエン『日本占領革命』上下、TBSブリタニカ1983年)。ところが、1946年の9月に、国鉄、海員のゼネストの話があって、国鉄もストライキをすると決めるし、海員組合もストを決めた。実際、海員組合は、ストをやった。海員組合のストは何と言っても船がないから、影響力は限られていたけれど、国鉄がストライキしたら、それこそ交通・物流がマヒしてしまう。コーエンは、当然、占領軍は、国鉄のストライキを禁止すると思っていたと書いています。ところが、マッカーサーは禁止しろと言わなかった。そうすると、ストライキされちゃうから、運輸省としてはどうしょうもない。全面的に白旗を掲げて解雇を撤回してしまった。
次は、1946年10月闘争で、電産がストライキするといって、実際にした。最初は、ごく短時間のスト(5分間)をした。そのころの映画をみると「ガチャン」と、労働者が電源を切っています。ストライキは、正しくはウオークアウトだから、仕事を放棄して、職場から出てくるというふうにしないといけないのに「ガチャン」と電源を落としています。これは、まあシンボリックなストで、それほど実害はない。第二波は、全国330工場への午前中4時間送電停止で、事業への影響は大きかった。ただし、占領軍関係施設などは対象から除外されていた。中労委が一所懸命調停して、なんとか妥協案をつくったのだけれど、それは賃金抑制政策に反するからダメだといって、内閣がけった。電力会社は、政府のいうことを聞く。たぶん、内閣がけったというより、GHQがけったと、ぼくは思う。そのころの日本政府は傀儡政権だから、重要な決定に責任を負ってやっていたのはGHQだった。末弘先生がせっかく中労委がなんとかまとめたのに、政府が横やりを出してけしからんと、カンカンに怒って、そんなこと言うなら、おれたち知らないから勝手にやれということになった。今度は、電産が、全国で12月2日から毎日午後5時間の停電ストをやることを決めた(外国公館や、停電が破壊的な影響を及ぼす事業所などを除く)。政府は、占領軍が占領目的違反で止めてくれるだろうと期待したと思うが、とめてくれなかった。ということは、産別会議の側からいうと、大丈夫だ、占領軍施設や事業に影響を及ぼさないようにすれば、ストライキはとめないんだというように、二回の経験から思ったんじゃないか。しかし、さすがに2・1ゼネストは影響が大きすぎる。それに、国鉄・海員は解雇反対スト、電産は、賃上げストで経済的要求を実現するためのものだったが、2・1ストは経済要求は建前で、本音は、政権奪取だということが明らかだったから、そんなものは認められないということになったのじゃないか。
<小休憩>
1948年に占領政策が大きく転換しました。なぜ転換したのか、いろんな理由があったと思いますが、一番底流にあったのは、共産党がやっていることは信用ならないということで、共産党がコントロールしている労働運動をクラッシュする。それで、まず、公務員の組合からスト権ばかりか、団体交渉権もとりあげてしまった。これが致命的な打撃だった。労働運動の主力部隊だったわけだから。次に、労組法を改正して、組合費だけで生活しろとか、既得権の労働協約は期限がきたら失効だということにした。最後はレッドパージがあった。これらが強烈なインパクトを、労働運動に与えたことは間違いない。
レッドパージに至ったのは、国際情勢の影響も大きかった。1950年6月には朝鮮戦争が始まりました。北朝鮮の戦車が攻め込んできて、韓国軍・米軍は釜山まで押し込まれた。冷戦どころか、熱戦です。1949年10月には中華人民共和国成立で、国共内戦の帰結が明白になっていた。ソ連の満州占領を起点とする共産党勢力拡大の波が、中国大陸から朝鮮半島の方に流れ込んで来ており、とめられない。米軍が本気になってこれを押し返そうと反攻を始めていた。1950年9月15日の仁川上陸作戦でマッカーサーが戦況を逆転することに成功するわけです。それまでは、まるで第二次大戦中のダンケルク撤退作戦が今にも始まろうかという情勢でした。日本の共産党の方はといえば、50年1月にコミンフォルム(国際共産党組織)の強烈な批判を受けて、解放軍規定や占領下の平和革命という従来路線を全面的に転換して、東アジアの共産党革命戦略に沿った運動方針に移行せざるをえなくなります。占領軍に反対する暴力革命路線に転換するわけですから、占領軍に弾圧されることになります。50年7月には新聞関係からレッドパージが始まります。
占領軍の方針転換によって、ガラガラと産別会議が崩壊してしまったわけですが、それを見ていた末弘厳太郎先生や大河内一男先生が、これはいったい何なんだと。占領軍がやれといったからやって、それが支持されないとなったら、やめちゃうのかと、すごくがっかりしたというのは分からんでもない。 大河内先生の『戦後日本労働運動』を読み返してみると、先生、それはあまりにもひどいんではありませんか、と言いたくなる。「時の権力に対する抵抗力において、いちじるしく卑屈である点に、日本の労働者、というより日本人自身の、特殊性格を見出すことができるのではないか。時の権力に弱いという日本人の事大思想は、労働者階級の場合にも、不幸にして、色濃くあらわれている」。そこまで言うか、というぐらい強烈でしょう。これじゃ、日本の労働者が自前の労働運動を作り出すなどということは、夢のまた夢ということになってしまう。まあ、そういうことを言われるくらい労働運動が落ち込んだことは確かだ。
組織人員が100万人減っただけではなくて、組織が空洞になってしまった。論文では鶴鉄労組の話を書きましたけど、みんな怖がって、役員を引き受けたがらない。鶴鉄労組といえば、戦後労働運動史では有名な先進組合で、最初に生産管理闘争をやった組合の一つなんだけど、それがこういうありさまだからね。どうやってそれを立て直すのか。
戦後直後の時期には、インテリが大勢、労働運動に参加していました。企業別組合の中心に多くのホワイトカラー層が加わっていただけでなく、外から、運動に飛びこむ人が多数いた。萩澤先生は東大の学生で、司法試験に通ったばかりのときに、産別書記局にいた高校同級の友人(大谷徹太郎、のち新産別)に誘われて産別書記局に入った。舟橋尚道先生は、全炭の書記局といった具合だった。氏原正治郎先生は、産別の調査部を無給のボランティアでやっていた。大河内先生のまわりの若手のインテリの人たちが、こぞって産別会議の応援団に入っていたんだね。そういう人たちが産別会議が雲散霧消してしまって行き場がないから、大学に戻ってきて、大学の先生になるとかそういう話があった時代です。
この落ち込むだけ落ち込んだ労働運動をどうやって立て直すかが、第四期組織化運動の課題だった。
立て直しには、一つは、産別会議壊滅のあとを受けて、ナショナルセンターをどう再建するかという上からの運動が必要で、もう一つは、下から、企業別組合を活性化させ、元気にして、下から声をくみあげて、運動を起こす。両方の動きを組み合わせて、再建を進める必要があった。
上からの運動ですが、これは1950年7月の総評結成が大きな節目になります。総評結成はGHQの陰謀だという説があって、私はそれは間違いだと思っています。GHQが産別会議壊滅後、非共産党系の統一的ナショナルセンターができることを希望して、いろいろと手を入れたことは確かのようですが。ブラッティなどのGHQ労働課の連中が総評の組織を構想できたかというと、そんなはずはない。総評は、なにか外国のモデルに基づいてできた組織ではなく、現場で運動をしていた日本の労働運動家が自らの必要性に基づいて作り上げた組織です。
総評結成の背景にあったのは、市場経済化です。ドッジラインまでは、日本は統制経済だった。戦時期に比べればたがが緩んで闇経済がはびこっているけれど、基本は統制経済だった。いろんな価格統制もされる。数量統制もしている。補助金もやっている。それが、ドッジラインでいっぺんに取り払われてしまった。計画経済がいっぺんに市場経済になってしまった。そりゃ、たいへんです、やらされる方は。市場経済で、企業は競争していかないと沈没してしまう。中小の炭鉱なんかは、バタバタ潰れたんです。統制経済のときは、エネルギーが足りないからといって、生産条件の悪い炭鉱にも補助金をだして、石炭を、増やせ増やせと言って生産していた。それがいっぺんになくなったから、零細炭鉱は潰れるしかない。
大手の炭鉱も、すぐ潰れはしないけれど、お互い同士価格競争しなければいけない。そういうことになると、企業別組合が賃上げを要求しても、「出せません、他社との競争があるから、わが社だけ高い賃金は出せません」と言われて、門前払いになってしまう。それに対しては、やはり、同じマーケットにいる企業の労働組合がみんな集まって、産業別統一闘争しなくてはならない。そうしなかったら、賃金なんか上がらないわけだ。それは、だれかに教わらなくても、運動をやっていれば分かる。産業別統一闘争をやるためには、産業別組織は一個で、主要な企業を網羅していなければならない。産別系と総同盟系と別れているてはダメで、統一行動をできるように組織を整えなくてはだめだ。
だから、産業別整理が総評結成の最大の旗印になった。産業別整理は、それまで、総同盟と産別会議、さらには中立とかに別れていた企業別組合の組織を、一つの産業別組織に集めて、整理をする。総評結成前後に、いっせいに進んでいます。最初のモデルケースが炭労だった。公務員の方は、ストライキ権を取り上げられているし、それを前提にしてどうやって運動していくのかが最大の問題ですが、民間は、産業別整理が第一です。官公労は、法改正で運動の前面から後退したから、民間主導でやらないといけない。民間主導するには、産業別組織を整備しなければならない。この時期にできた代表的な産業別組織が、合化労連と鉄鋼労連。そのあと、やや遅れて電機労連ができる。この時期に、産業別組織の整備が進みました。もっとも、進まなかった産業もあって、代表的なのは造船業界です。
ところで、総同盟は、産別が潰れて、生き残ったおれたちの天下だと思っていたんだけど、そうはならない。最初はそうやろうとした。高野実が総同盟の総主事に当選していたんだけど、1949年2月に全労会議というのを作ろうとした。総同盟と産別民同と、国労民同とが組んで、新しい全労会議という全国組織を立ち上げようとした。だけどそれには、できつつある産業別組織は熱心じゃなかった。この間の事情については、よく分からないところもありますが、決定的だったのが、炭労の動きだったと思います。炭労は総同盟と衝突することになる。
炭鉱の労働運動は、産別系、総同盟系、中立系と三つに分かれていたけれど、産別会議の没落という情勢の中で、統一的産業別組織結成の動きがでてきた。産業別整理して、産業別統一闘争をやろう、そのためには、炭労に一本化して、組織力をつけて、大手企業組合を勢ぞろいさせて、いっせいに統一ストライキができる態勢にしようとした。そのためには、炭労の会費をあげないといけない。専従もおいて束ねるような運動ができるようにしないといけない。ところが、当時の炭労には、日鉱同盟が団体加盟していた。傘下の組織は、二重に上部団体費を払わないといけないことになる。日鉱同盟に配慮すると、炭労の組合費なんか、そんなに高くできない。それでは困るから、日鉱同盟傘下の組合が日鉱同盟をご破算にして、単組として炭労に入ってくれないかというのが企業別組合側からの自然な期待になる。
ところがそれは、総同盟からいったら、とんでもない話で、嫌だということになった。おまえらが、おれたちの方に入ってくればいいじゃないかということになる。大手組合の連中がそういう気持ちにならなかった理由は、定かではないけれど、日鉱同盟の既存幹部の支配下にはいるのは嫌だと思ったのかもしれない。結局、対立を起こして、日鉱同盟はせっかくの統一組織炭労から出て行ってしまった。こういう状況では、総同盟主導の労働戦線統一なんかできない。総同盟は、自分たちが解体したくない。金属や化学の分野では、もっと大変で、産業別整理のために、自分たちの組織を解体しなければならないことになる。そこまでは、なかなか踏み切れない。
産別民同の方も、事情は似ている。まず、自分たちを全国組織にして、その上で総同盟と組んで、全国組織の同盟体をつくるというイメージなんだけど、産別民同というのは弱体な組織で、しっかりした労働組合全国組織を作れない。もともと、産別は、共産党で成り立っていたわけです。細谷たちが共産党に対抗できるような組織をつくろうとしても、それは無理です。私鉄総連が提唱した1949年11月1日の統一準備会は、総同盟にも、産別にも所属していない中立の民間産別に呼びかけて、そこから再編成をスタートさせた。ナショナルセンター主導でなく、産別組織主導の再編成ということになった。
産別整理を基本とする産別組織主導の戦線統一となると、総同盟はたいへんなことになる。例えば、総同盟神奈川県連の主力メンバーだった日本鋼管川崎製鉄所の組合が鉄鋼労連をつくるために神奈川金属の組織から抜ければ、既存の神奈川金属の組織はガタガタになってしまう。組合費が入ってこなくなる。残るのは中小企業だけになる。そこに踏み切るのはたいへんだったわけで、だから、高野だって最初はそこまで考えていなかったと思う。高野の力の源泉になっている組織基盤は関東金属だから、産別主導の再編に踏み切るということは、自分の組織にも火が飛び込んでくる。だけど、それに高野は踏み切った。だから、高野というのはすごい人物だと、私は思っています。いろいろ政治的な思惑はあったと思う。この機会に、総同盟右派をやっつけようとか、いろいろ考えたと思うけど、とにもかくにも総同盟を解体して、産業別整理をしたから、その後の労働運動の基本的な組織体制ができあがったことは確かです。
だから、産別といっても、大産別ではなく、中産別であって、同じ市場で競争している企業の労働組合が集まって、それで産業別統一闘争をすることを主な役目にして運動する組織体制に転換した。それについては、例えば全繊なんかも否定できなかったと思います。全繊は、総同盟の主力組合だったのですが、総評ができたときにメンバーになっているし、総同盟解体に反対して総同盟を残した小さなグループがあったわけだけれど、全繊は、それに同調しなかった。
それは結局、産業別整理というのは正しい方向だと思う企業別組合が多くて、そこから簡単に飛び出せないということだったのではないか。全繊が海員組合といっしょに総評から飛び出すのは、1953年になってからで、総同盟と全労会議を作ったのが1954年です。全繊や海員組合が総同盟に入ったわけではない。全労という協議体をつくって、そこに、小規模なナショナルセンターである総同盟と産業別組織である海員組合と全繊同盟が集まるという体制で、複雑な組織となった。最終的に、1964年に同盟となるときに総同盟を解散しなければならなくなる。
だから、総評結成に至る基本的な動力は、上に説明してきたような企業別組合やそれが集まった産業別連合体の内発的ニーズにあり、占領軍がいろいろ画策したとか、そういう陰謀説は、あったとしても、副次的なものだったと考えています。
第二部
【石原】ありがとうございました。ご丁寧に説明をいただきましたので、あとはざっくばらんで脈絡のない話になるかもしれませんけど、先生のお話をおうかがいして、いくつか質問させていただきたいと思います。
その前に、私、昭和の時代というのは、自分が生まれて育った時代なんですけど、どちらかというと大正時代の方が好きでして、ですから、この年代は存じ上げなくて、それが今回、鼎談に加藤さんからお招きいただいて、仁田先生のお話を聞かせていただく機会ができて、ひじょうにいろんな勉強になったことがあり、また、発見があって、とても感謝しています。ぜひ、今日のお話も含めて、もう一度、私なりにこの時代を見つめてみたいと思っています。
最初に、私の発見というか気づいたことですけど、戦争の最中の昭和17年、1952年秋に、すでにアメリカ国務省内で占領政策のあり方について検討がスタートしていて、無条件降伏にどのようにもっていくか、天皇制を存続させるのかどうかとか、このようなことが戦争の終わる3年ぐらい前から検討されていて、44年1月には、戦後の計画委員会、政策を立案する機関を国務省内で本格化させているなど、私にとっては、新鮮で驚きでした。
もう一つの発見は、GHQのメンバーはエリートぞろいだった。日本のような小さな国の占領なのに、優秀なメンバーが集結していて、大卒、大学院卒が大半、しかもこの中にはロースクール出身者もいて、専門家が日本に乗り込んできている。アメリカに帰ったあとも、それぞれ、弁護士や高級官僚などになって、重要なポジションで活躍されています。
それと、先生の論文にも触れられているのですが、とくに公務員の争議権について、GHQ内部で大論争が行われている。できあがったばかりの日本の憲法に対して、公務員に争議権を与えないというのは、断じてならないと言って、それでアメリカに帰ってしまった課長のキレンとか、占領政策を担った人たちというのは、本気で日本のことを考えて、日本の民主化のために精力を傾けた人たち。ですから、安易な妥協をしないでぶつかり合っているのですが、このような姿勢に感銘を受けました。
その前提で、いくつか雑談的になってしまうのですが、末弘先生のご本で、企業別組合ということだけではなしに、日本の労働組合というのは、世界からみたとき、非常識な部分が多い。具体的には、高級従業員が組合に加入している、ユニオンショップが多い、失業後の世話を担わない、それに、専従役員の賃金も会社丸抱えになっているし、労働協約もいったん締結すれば、無制限に延長できる。こういう企業別組合だけではなしに、日本の組合の特異な姿ですね、いったい末弘先生とか優秀な方々がいらっしゃったのに、先ほどのお話で、官僚のつくった、官僚の思い入れでできあがった労組法ということなんですけど、旧労働組合法は、私には不可解なところがあって、このあたりどう理解すればいいのでしょうか。
【仁田】戦前の労組法の印象が強かったのではと思います。労働組合法は、一種の法人法のようにも見えます。法人の名称があって、所在地とかを書く。法人的なのを労働者につくらせるとか、法人を義務化しようという法案で、労働組合に名を借りて変な組織ができては困る。そういう法人取り締まり的発想が出発点になっていた気がします。
しかし、旧労組法のこういう取り締まり規定は、実際は発動されていないと思う。解散させられた労働組合もないでしょう。労働組合を団体として取り締まる。不当なことを労働組合が行えば、知事が何とかする、といったことは、実際はなかったのではないか思う。また、できるような状況ではなかったしね。
【石原】戦前の労組法の検討では、労働組合は届出制とか、定められた規約に不適当な条文があれば、裁判所が変更命令を出せるとか、行政の介入が問題視されて、帝国議会では成立しなかったと思うのですが。
【仁田】戦前、成立しなかったのは、そういう理由ではなく、それだけ取り締まるから大丈夫と言われても、使用者側が受け入れなかったという理由です。戦後、そういう規制はいらなかったんじゃないか、自由に組合をつくらせているし。どうして、規約の変更権とか必要だと考えたのか。労務法制審議委員会の検討では、末弘さんだけではなくて、西尾や松岡も入っていたわけだからね。それでも、こんなのが必要と思っていたということは、単純化して言えば、戦前の名残というか、それぐらいは必要だねとなったのはなぜなのか。まあ、労働組合は所得税法人税免税にするので、それを悪用して免税事業をやろうという輩があらわれるのではないかというようなお役人的発想があったのかも。
【石原】昭和24年になって、旧労働組合法に代えて、新労働組合法をつくらないといけないと言い出したのはどちらなんでしょう。
【仁田】それは占領軍。英語で原案を書いてきて、これを翻訳しろと言って。
【石原】持ち込みですか。
【仁田】完全な持ち込み。
【石原】旧は和製だけど、新はアメリカですね。
【仁田】審議会もなかったからね。やはり、日本人にやらせていてはダメだ。だから、アメリカの、ちゃんとした労働組合法を日本人にもやらせようと。最初の案では、交渉単位制だってあった。ところが、ごちゃごちゃうるさく言うものだから、まともに議論していたら、とんでもない時間がかかってしまう。いつになったらできるか分からない、速成栽培でやらないといけないから、この程度でいいかという感じで、GHQが妥協したと思う。
【石原】アメリカでは、戦前のワグナー法から、戦後にタフトハートレー法に変わっています。これ、改悪だとして労働組合の評判も悪かったというのを、何かで読んだことがあるのですが、これが新労働組合法の議論に影響していませんか。
【仁田】タフトハートレー法が、日本の労働組合改正に影響しているということは、余りないと思う。
要は、日本の労使関係の現状をなんとかしなければいけない。経営側がいちばん困ったのは、労働協約の自動更新で、人事同意約款が含まれている協約が解除できないから、永遠にリストラできない。それを否認するために、自動更新そのものを否定した。だけど、嫌になったら、期限がきたらどんな協約も、はい解消、なくなりましたということになるのか、疑問があります。
労働協約には、たいてい労使協議制、経営協議会の条項がある。経営協議会でちゃんと発言できますよ、しかるべき経営情報を組合に提供しますよ、という債務的条項です。そういう労使関係の核心に関わる条項が、協約はあくまで同意にもとづくんだから、嫌だとなれば、一方的にチャラにできますというようにしていいのか。この当時、法律家が協約の余後効という議論をした。協約が期限切れになっても、その効力が全部なくなることはないという議論です。この時は、賃金とか、そういう規範的部分について余後効があるということでした。労使関係学者としては、むしろ、債務的部分の発言権保障のほうが大事ではないか。いままで、労使協議制・経営協議会で発言権を保障して、それが労使関係の基本を形成していたのに、いきなり一方の都合でチャラにしていいのか。それは、事実上団交拒否で、不当労働行為になるのじゃないか。ヘッジファンドが来て、会社を買って、いきなり無協約にします。そのときに、今まであった既得権をゼロにできるのか。それはやはり、労使関係の安定性を損なうから、労使協議制については、最低、これぐらいのことはやらないといけないとか、何だったら法律に書けばいいんだけど、債務的事項について余後効があるということにするか、何かしなければいけないんじゃないか。
労使関係の基本という点でいえば、ユニオン・ショップだって、いきなりそれを破棄されたら組合は困る。
労組法改正で大きな問題になったもう一つの論点は、経費援助で、とくに組合役員の人件費保障で、これを一律認めないことにしてしまった。確かに、組合長以下、給料もらいながら組合運動を無制限にできるというのは、行き過ぎじゃないかと思いますが、一切いけないというのは逆に行きすぎではないか。組合活動に使う時間の人件費を保障するというのはおかしいことではない。ある程度、そういうものを保障しなかったら、職場の労働組合なんか活動できない。だって、普通は、労働組合経営学では、組合員500人に一人、専従がおける。
【加藤】350人で最低一人。ぼくの計算ではね。
【仁田】それは、若い組合員役員の場合でしょう。で、一人で350人、めんどうを見切れますか。みんなが職場で、あれしてくれ、どうにかしてくれと言ってきたら、一人で350人の面倒を見るのは無理ですよ。じゃあ、仕事を終えた後、夜に、完全ボランティアでやれますか。それは無理でしょう。世界中でそんなことしていませんよ。アメリカだって時間外、組合活動を認めていて、何時間分か有給でやっていいよとか、何人かは事実上専従で活動してよいということにしている。そういう協定を作っても不当労働行為にならない。ドイツやフランスだったら、その役は従業員代表制でお金をもらって、事実上組合員の面倒をみているわけです。スウエーデンだったら、そういう制度はないから、職場の組合活動家に、会社が人件費を負担する。そういうようにやっているわけだよね。職場で、日常的に労働生活に広く関与する労働運動をやろうとしたら、こういうものは必要なんです。日本は、それを全部、組合費で、組合が自前でやれという話になっているから、そこには無理がある。
1948年末からGHQがやった経費援助退治のための協約の見直し行政指導のとき、一日、2時間ぐらいの便宜供与で時間内組合活動をさせてもいいという文書を出しているんですね。
【石原】その便宜供与は、不当労働行為にはあたらないと。
【仁田】もちろん、あたらない。それぐらいは、アメリカでみんなやっているんだから、現場を踏んでいた労働専門家は分かっていたはずです。だけど、労組法改正案に、理由は分からないけれど、この条項は入らなかった。こういうものを全部なしで、日本の労働組合に活動やれというのは過酷だということは知っていたはずです。しかし、共産党の専従活動家を退治しなくてはならないとか、いろいろ政治的な思惑を抱えていたから、これでもしょうがないということで、やったんじゃないか。
残念なのは、そのときに学者も、運動家の側も、別に悪くないと、少しぐらいお金を払ってやっても、会社のプラスにもなるし、時間内に組合活動させてもいいじゃないかと居直らなかったこと。組合側の反論が情けない。日本の労働者は賃金が低いから、組合費も払えないので、会社に負担してもらわなきゃいけない、などと言っている。堂々と、これは労使関係をきちんと運営していくうえで必要な、会社が負担すべきコストなんですと、どうして反論できなかったのか。野放図にやってはいけないかもしれないけど、一日2時間まではやっていいとか、ルールをつくってやればいい。GHQだって、最初はそう指導しているんだから。これが、労組法改正の議論の中で消えてしまった。日本の学者も運動側も、知らなかったんだ、アメリカで便宜供与をやっていることを。
【加藤】そうでしょうね。
【仁田】全部、自前の組合費でやっているかのように、思っちゃった。確かに本には便宜供与の話は書いてない。いちばん肝心なことなんだけど。
【加藤】大事なことは書いてない。
【仁田】現地に行って、そこで暮らしてみればすぐに分かることなのだけど、教科書を読んでいただけでは分からない。だけど戦後直後の時期に、とても海外調査なんてできないからね。統計もない。そういうのに気づいたのは、やっと小池先生が在外研究で現地調査をして初めて。
【加藤】68年、70年ごろから。
【仁田】70年ごろから、やっと海外に調査に行けるようになって、いろいろ現地で話を聞いて調べてみると、そうらしいということが分かった。
【石原】苦情処理に関連して、話がそれるかもしれませんが、苦情処理とか個別紛争の解決、これが企業別組合であるがゆえに、弱さになっているのではないかというのがあります。労働審判員をやっているけど、本来、こんなの、組合活動で、何で解決しないの、会社と話せばすむのではないか。それを労働審判の場に持ち込んでくるんですかと感じることが、ままあります。また、合同労組の場合、個別紛争を労働委員会に持ち込む、団交拒否の不当労働行為で。こういうケースに接するたびに、労使関係が企業別であるがゆえに、当事者解決に至らない、その弱さが出てしまっているのではないかと思うことがあります。
【仁田】私は、法律上、職場苦情処理委員を置かなければならないということにして、法律に定めて、一定の時間内活動を認めますとすればいいのじゃないか。私は国士舘大学に勤務しているときに、ハラスメント相談員というのになったけれど、一人も相談に来なかった。こんなもの、無給で機能するはずない。やはり、一日2時間までいかなくても、たとえば週に3時間ぐらいでも、相談時間を設けますからきてくださいということにしなければ、だめでしょう。
まあ、ハラスメントの事件については、そもそも専従する人を置かなければ、ぜったいに機能しない。教授が片手間でやっていては、ダメなんだ。
ハラスメントに限らず、職場には、不満があったり不安があったりするでしょう。だから、組合がちゃんとやればいいんだけど、組合だって忙しいから、そんな細々とめんどうをみてられない。だからやはり、お金を払って、職場苦情処理委員を置くようにしないと。もちろん、それを組合が代行してやってもいいですが、時間内組合活動を認めてもらわないと。そういうことを、ちゃんと考えてあげないで、めんどうをみてもらえないとか、批判してもね。
【石原】法によって、パワハラとかセクハラ、苦情処理委員会をおかなければいけないけど、現実、兼務している場合が多い。専任の窓口を置いて、相談を受け付けるというのは少ない。だから、実効性という意味では問題ですね。労働審判制度ももちろん大事ですが、やはり組合の職場活動の中で解決すべきものは、そこで解決すべきでしょう。
【仁田】セクハラなどは、外の相談員をおいた方がいい場合もあるでしょうが、労働審判に出てくるような、パワハラとかは、組合の職場活動で解決すべきものが多いのではないか。だから、職場苦情処理を制度化しなければならないということにすれば、会社もやらなければいけないというのが分かるし、組合としてもやりやすいんじゃないか。
【加藤】組織率が、今16.8%(2019年)という2割を切った現状で、去年のはまだ聞いていませんが、組織率の低い状況において、非組織化の83.2%のエリアで発生している苦情処理という課題がどういう形で処理されいくのかというのがあるのではないか。組織化されているところは、組合役員がいるのであれば組合活動の中で、6割か7割は処理できるのではないか。
パワハラとかは労使関係から個別に派生する問題であって、非組織である83.2%の領域での処理という意味では、委員制度を置くといった仕組みをつくって問題解決するというのが現実的だと思いますが、それをすると労働組合はいらないのではないかという、逆説的な証明になってしまうという反論が起こり得るという現実があるから、はかばかしくない。
【石原】企業別組合の弱さと言ったんですけど、組合と相談しても、結局、会社と一緒だから、相談しても解決してくんないんでしょうという声がある。だから、真摯に聞くところは聞いてあげて、親身にならないといけないと思うのですけど。とにかく、司法の場に持ち込むまえに、そんなの労働相談とか、基準監督署とか、連合の労働相談室に電話すればいいんだけど、そのあたり機能していない。実効性という意味では、課題を抱えているのではないでしょうか。
【加藤】そういうことから言えば、企業別の労組が原因ではなくて、普通の制度でも会社にどうせ筒抜けでしょうと、内部通報制度が実はそうなんですけど、内部通報では全部抜けていたとか、問題解決にならないとすれば、外部の組織を使うしかない。ADRをもっと充実して、陣容を強化して気楽にどうぞ、という態勢の方が、現実の対応としてはいいような気がする。
【仁田】合同労組というのは、やっている人の顔みてごらん。みんな年寄りだよ。
【加藤】団塊の世代ですね。
【仁田】ぼくらの世代が多いけど、近い将来、いなくなっちゃう可能性がある。左翼なんてものが存在しなくなって、若い人の中からこういう運動を担う人がなかなか出てきにくい。だから、今、コミュニティユニオンが若い人を調達してくるのは、難しい世の中になっている。あれが、そのまま続くかどうかは分からない。
どうやって、コミュニティユニオンみたいな組織を再生産させていくかは、結構、やっかいな課題ではないか。
制度的な対応として、従業員代表制を法制化するという話がある。でも、従業員の代表を選ぶと、その人たちが会社に何か言いに行くというような想定をしているわけだ。だけど、従業員代表が職場苦情処理するなどということは、どこにも書いてない。あくまで意思疎通機関だから。となると、従業員代表制プラス職場苦情処理制度みたいなものを制度化しないと、実効性があがらないんじゃないかと。そうなると、ますます労働組合との関係が難しくなる。
【加藤】労働組合と同じものをつくることになる。
【仁田】だから、ぼくの説は、もう、労基法36条の規定を変更して、「36協定は労働組合としか結べない」としたらいいんじゃないか。労働組合がない職場では残業ができないんだから、労働組合組織率がいっぺんに50%を超えるだろう。
【加藤】過半数従業員代表と協定を結ぶことに今はなっているが、それを認めないと。
【仁田】36協定、あれは特例で認めているんだからね。本来過半数労働組合と結ばなくてはいけないのに、それがないときは、過半数代表でもいいと。だから、例外をやめにして、過半数代表なんか労働者を代表する権能をもてるはずがないから、実績に鑑みて、これはダメとすればいいだけの話。そもそも、労働時間は週40時間と決まっているので、その例外として残業協定を結べば残業させてよいということなんで、ここですでに例外扱いが入っている。それにもう一つ、特例を重ねるというのは、やり過ぎじゃないのという意見です。こういうことを書いたら、「仁田先生、また乱暴なことを言ってますね」というようなコメントしかいただいてないですけどね。
【加藤】そろそろ時間ですが、最後にどうですか。
【石原】一点すみません。総評結成の背景とか、GHQが絡んだものではないとご説明があったんですが、そこは理解しつつも、わずか1年後か2年後に、総評は転回してしまいます。これが、不幸な結果を生み、長い間、引きずるのですが、このあたりの背景はどう考えればいいのでしょうか。
【仁田】いきさつをみていくと、朝鮮戦争の影響がやはり大きいと思います。国際政治にからむ政治的な対立が労働運動にも大きく影響した。つまり、多数の国民は、戦争はもうふるふる嫌だと思っている。朝鮮戦争の状況を見ると、うっかりすると、向こうに連れていかれるおそれがある。朝鮮半島に自衛隊が出征するとか、自衛隊じゃ足りなくて、日本陸軍復活・徴兵制復活というようになって。そういう状況ですよ。よそから、オーストラリア人なんかまで国連軍来て、大勢、死んでいるんだから。すぐそばで。火の手があがっているわけですよ。北朝鮮と韓国が闘っているだけじゃない。こちらは米軍から国連軍、あちらは国共内戦を勝ち抜いた膨大な人民解放軍の戦力プラス、その背後にソ連がついていて、ソ連の重戦車がたくさん前線にでてきているし、空ではミグ戦闘機と空中戦をしているわけです。だから、冷戦ではなく、熱戦です。もう半分第三次世界大戦という形勢なわけです。
そのときに、みんな、すごい危機意識を抱くわけです。そりゃ、無理からぬと思う。今、北朝鮮と韓国が戦争を始めてごらん。今だったらもっとたいへんだ。ミサイルが飛んで来ちゃうから。だから、そういう状況で、労働組合が再建される。そのときに、政治問題、外交問題は、労働組合の本務じゃないといっても、やはり平和四原則とか言われると、そうだよなと考える組合員がたくさんいる。国際自由労連と一緒になって、国連軍賛成とは、なかなかならない。やはり、戦争には参加したくない。現に憲法9条があるじゃないか、これを守ってくれ。単独講和したら、ソ連と交戦状態が続くのだから、日本にも攻めてくるんじゃないか。そういうことが、左右対立の政治の中で、かなり重要な位置を占めていた。やはり政治的な状況で、労働組合も、政党支持は自由ですといえない。憲法は改正されたくないし、戦争には絶対に行きたくない。まだ、戦争が終わって10年たってなかったわけだ。
【加藤】まだ、わずか5年ですよね。
【仁田】まだ5年だ。ついこの間まで、戦争していて、大勢、死んでいる。空から爆弾が落ちてきていたわけでしょう。国民・組合員が、憲法9条はいい、これでいったら、火の粉をかぶらないですまされるんではないかと。それは極ごく、自然な反応だと思う。もう戦争は嫌だと思うのは、無理からぬところがある。
でも、その感情に素直に従って政治行動すると、自由主義陣営の団結は保てないし、国際信義は守れない。国際自由労連に入って、共産圏の武力侵略は許されないと言うべきだと、いくら右派の人たちが言っても、みんな賛成する気にならなかった。それはある程度、仕方なかったんじゃないかなという気がする。
ぼくが思うのは、1955年に事務局長選挙で敗れて高野が退場したときに、一応、全繊やなんかが総評に戻ってくるチャンスがあったんじゃないか。左右社会党が合同しているし。実際に、そういう話は、あったわけだ。結局、いったん別れた以上、できませんということになったみたいだけど。まあ、総評の主力部隊は、やや左だし、四原則をやめるわけじゃない。結局、それは立ち消えになっちゃった。でも、あのときに、太田や岩井たちがうまくやっていれば、統一できた可能性があるという気がしないでもない。それがなぜ、できなかったのか。これも歴史研究のテーマです。だれもそんなこと真剣に考えていないから、研究しないんだけど。
【石原】加藤さんがいらっしゃるから、あれですけど、何十年が経っても、今も、労働運動において、政党との関係が問題となっている。連合の路線問題ですね。課題を突き付けたりしている。
【加藤】だれが?(笑)
【石原】この状態というのはいつまで続くのかな。日本の労働運動の中で、政党支持問題は、離れたり、近づいたりと。
【加藤】やや離れたり、くっついたり。余韻のあるところで、今日はありがとうございました。
-了-
【研究会抄録】バックナンバー
- 【】「政治と労働の接点-これからの政治参加の傾向と対策-」 講師:岡崎敏弘様、難波奨二様、オブ参加者様
- 【】ウェブ座談会シリーズ2「世の中何が問題か-振りかえる兵庫知事選とSNS選挙の行方」 講師:座談会は五十音順に伊藤、江目、佐藤、中堤、渡邊の各氏、司会は加藤、事務局は藤田
- 【】ウェブ座談会シリーズ1「世の中何が問題なのか-アラコキ(古希)連が斬りまくる」 講師:参加者は五十音順で伊藤、江目、佐藤、中堤、三井各氏。司会は加藤、事務局は平川。
- 【】ウェブ鼎談シリーズ第(14回)「戦後の労働運動に学ぶ」 講師:仁田道夫氏、石原康則氏
- 【】ウェブ鼎談シリーズ(第13回) 「労働者協同組合法について」 講師:山本幸司氏、山根木晴久氏
- 【】ウェブ鼎談シリーズ(第12回)「戦前の労働運動に学ぶ」 講師:仁田道夫氏、石原康則氏
- 【】ウェブ鼎談シリーズ(第11回) 「労働運動の昨日今日明日ー障害者雇用・就業支援の実践と課題について」 講師:鈴木巌氏、石原康則氏
- 【】バーチャルセミナー「あらためて労働組合と政治」 講師:一の橋政策研究会 代表 加藤敏幸
- 【】ウェブ鼎談シリーズ(第10回)「労働運動の昨日今日明日ー労働運動と生産性ー」 講師:山﨑弦一氏、中堤康方氏
- 【】ウェブ鼎談シリーズ(第9回)「労働運動の昨日今日明日ー官公労働運動について②ー」 講師:山本 幸司氏、吉澤 伸夫氏